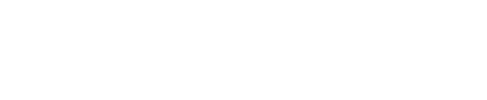コールセンターの稼働率とは?適正値や占有率との違いを解説

コールセンターの業務効率化を実現するためには、様々な数値化されたデータが規準となります。その中でも「適正値」や「占有率」等の数値は非常に重要な意味を持つデータです。これらの意味を正確に理解し活用することで、センター内の人員整理や生産性の向上につながります。
では、実際的なコールセンターの「稼働率」や「適正値」「占有率」等にはどのような意味を持つのでしょうか。今回はこの3つについて、わかりやすくご紹介いたします。
コールセンターの稼働率とは?
コールセンターにおける「稼働率」とは、給与支払い時間内で、オペレーターが顧客対応にかける時間の割合のことを指します。
この給与支払い時間の中には、コールセンターでの顧客対応という本業(生産時間)の他にも、ミーティングや研修、休憩等の時間(非生産時間)が含まれます。
生産時間には、通話時間や保留時間、入力作業といった後処理に加え、電話を待機している時間も含まれます。稼働率がわかることにより、コールセンターのオペレーターが現場でどの程度稼働しているのか、時間の割合を把握することが可能になります。
コールセンターにおける「適正値」と「占有率」の重要性
コールセンターにおいて「適正値」と「占有率」という数値は非常に重要な意味を持ちます。具体的にはどのような意味合いを持つのか、この項目で詳しくご紹介いたします。
また、稼働率の目標設定の目安も記載していますので、コールンセンター運営の健全化への参考にして下さい。
稼働率における「適正値」とはどの程度?
コールセンターの国際的品質保証規格(COPC CX規格)では、月平均の稼働率の86%を指標値として定義しており、日本のコールセンターでも、一般的には80~85%が適切だといわれています。
また、稼働率の目標設定は、以下が目安となっています。
※0~70%:人員等の配置見直しライン(余剰人員が発生している)
※80~85%:適性ライン(コールセンターとして理想的な状態)
※85~90%:注意すべきライン(オペレーターが不足している等)
※90%以上:危険なライン(離職等の増加でサービスの質が低下する)
稼働率が80%を下回っている場合、入電に対してオペレーターが多い状態で、70%以下になると明らかに余剰人員がいることが予測できます。無駄な人件費がかかっている可能性があるため、人員配置の見直しが必要となります。
一方、稼働率が90%以上の場合には人手不足に陥っている可能性があります。オペレーターの業務量が多く、疲労やストレスにより顧客対応品質が低下する可能性があります。
オペレーターの心身にも負担をかけ、欠勤率の悪化や離職にもつながってしまいます。
稼働率と占有率の違いは?
稼働率と占有率は、どちらも「顧客対応時間」を表す数値なので混同しやすいものですが、厳密にいえば似て非なるものです。占有率とは、稼働率に対して待機時間を差し引いた数値になり、より直接的に顧客に関わっている時間の割合となります。
例えば、占有率が高ければ直接的に顧客対応をする時間が多いことになり、占有率が低ければ待機時間が長くなるという計算になります。
ただし、それぞれ分母が違いますので、必ずしも稼働率>占有率とはなりません。稼働率は、給与発生時間を分母とし、顧客からの電話のために「稼働している時間」の割合です。占有率は、稼働率を分母として、一顧客への対応に「占める」時間の割合となります。
なお、どちらの指標も「値が高ければ良い」という数値基準ではなく、オペレーターの業務量に応じて調整するのが大切となります。
稼働率を適切に管理したい!重要なポイントは?

稼働率をマネジメントすることにより、積極的な通話対応の品質向上や顧客満足度の向上、人員の定着に関わってきます。どのような点に注意して、稼働率を適切に管理すればいいのか、ここからはそのポイントについて詳しくご紹介いたします。
オペレーターのステータス管理に注意する
「通話中」「着信中」「後処理作業中」「離席中」等、オペレーターに自身のステータス管理を行ってもらうよう徹底することにより、より正確な稼働率の把握につながります。
オペレーターの「ちょっとした離席」を、どのステータスに設定して計算したかによっても、稼働率は変化します。また、管理者が客観的に稼働状況を管理することにより「他のオペレーターと比較して自分ばかりが電話対応をしている」というようなオペレーターの個人的な不満を事前に防ぐ効果もあります。
ただし、あまりにも細かくステータスを設定してしまうとオペレーターの手間となり、持続せず逆効果となってしまうことがあるので、注意が必要となります。
オペレーターの人員調整をこまめに行う
稼働率が適正値から大きく外れている場合には、1人1人のマンパワーだけに依存してしまうと、オペレーターへの負荷がかかりすぎることになってしまいます。
一方、稼働率が高い数値になっていても、オペレーターが多すぎて待機している時間が長くなっているという場合もあります。この場合は「オペレーターが多すぎる」と判断できるでしょう。しかし、オペレーターの数を減らして待機する間もないほど稼働率を高めてしまうと、電話がつながりづらくなり、顧客満足度の低下につながります。
電話がかかってくる数(入電数)に応じた、オペレーターの人数調整をこまめに行うことで、稼働率の改善が見込めます。バランスの取れた稼働率を模索していきましょう。
非生産時間を活用する
コールセンターには「繁忙期」と「閑散期」がよくあります。とはいえ、人件費を節約するために、コールセンターにとって都合の良い時間帯だけオペレーターに勤務してもらうわけにもいきません。
あらかじめ調べた入電予測によって、入電数の少ない曜日や時間帯がわかっていれば、その時間を新人研修や面談、業務内容の変化や追加に関する周知徹底等に使うのが効果的です。
オペレーターのスキルアップやモチベーションの向上につながり、将来的な面から見てもコールセンターにとって有益な時間となります。
オペレーターへの配慮を欠かさず、コンディション管理を行う
オペレーターの心身の健康を管理し、無理のない人員配置をすることも適正な稼働率を保つためには必要不可欠です。
慢性的に稼働率の高い状態は、オペレーターに強いストレスと疲労感をもたらします。稼働率が高すぎると非生産時間も限られてしまうため、教育のための時間や情報共有の時間も十分に確保できなくなる可能性があります。
オペレーターのストレスや負担をできるだけ軽減するには、まずは人員配置等の基礎的部分を適正化することが最も重要です。その上で「適切な評価制度を整備する」「在宅コールセンターをはじめとする柔軟な働き方を採用していく」といった、現代の働き方に即した工夫が求められます。
コールセンターシステムを導入する
稼働率を始めとしたデータの管理を効率的に行うには、コールセンターシステムの導入がお勧めです。
上記でご説明したような稼働率改善に必要なポイントを網羅・実践できる機能が備わっているため、総合的な対策が可能となります。
パソコンと電話を統合したCTIシステム、顧客情報管理のCRMシステムと連携し、電話応対業務を支援する他にも、オペレーターのステータス管理機能や対応履歴結果をデータベース化する機能等で、稼働率や占有率の集計や分析もスムーズに行えます。正確な測定により、継続的な改善も見込めるでしょう。
導入成功率98.7%!クラウド型CTIシステムMostableが選ばれています
コールセンターを開設するにあたり、CTIシステムは必要不可欠なものです。しかし、導入される企業様の運営方法や扱う商材によっても、適したCTIシステムは異なります。
Mostableは開発から今日まで、コールセンターを運営されている企業様と現場の声に着目し、顧客ニーズに応じた操作性や機能、サービスの向上を追求してまいりました。
運営側の視点だけではなく、現場の連携やバランスの取れたCTIシステムこそ、コールセンターにとって必要なシステムです。
特に「オペレーターの負担を軽減したい」というご意見をよく耳にします。高価なCTIシステムを導入したものの、複雑な機能が多すぎて操作が難しく、オペレーターが操作を覚えるのに時間がかかってしまっている、という現状もあります。
これを、Mostableは直感的に扱えるUI(ユーザーインターフェイス)で解決。採用から即戦力までの時間を短縮することが可能になりました。
導入成功率は驚異の98.7%!クラウド型CTIシステムなら、ぜひMostableをご検討下さい!